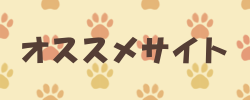プランづくりの基本知識
2018年1月1日「月曜日」更新の日記
-

- 快適で楽しい住まいづくりに向けて、やはり大切なのが間取りをはじめとしたプランづくりです。プランしだいで毎日の暮らしが大きく変わってくるだけに、実際の暮らしをイメージしてプランニングすることが重要です。
したがって、「これがベストプランだ」というような普遍的なプランは存在しません。ベストプランは、そのユーザーの家族構成やライフスタイル、年齢、職業、さらには趣味等によっても変わってくるものなのです。
ただ、普遍的なベストプランはなくても、プランニングにあたって知っておきたい基本知識はあります。ここでは、プランを検討するにあたって頻度が高いと思われるものに関して述べたいと思います。
まず、毎日の暮らしの中で最も使用頻度が高いのがキッチンでしょう。かつては「女性の城」と言われたキッチンですが、ライフスタイルの変化に伴ってLDKとの調和を重視したオープン型や対面式が登場するなどキッチンのあり方もだいぶ変わってきています。
「オープンキッチンの長所、短所」
LDKが広く使えるうえ、気軽に立ち入れるので誰もが調理や後かたづけに参加しやすい、コミュニケーション重視型のキッチンになるのがオープンキッチンです。
一方でキッチンがリビングから丸見えになるため、乱雑にしているとすぐ目に付いてしまいます。壁に接する部分も少なくなるので、カップボードや冷蔵庫の置き場所も問題になります。
「対面式キッチンの長所、短所」
セミオープンの対面式キッチンは、子どもの様子やテレビを見ながら家事ができるうえ、オープンキッチンで気になったキッチンの乱雑さが見えにくくなる点やカップボード、冷蔵庫のスペースも問題にならないことが長所です。
反面、ある程度広いスペースが必要な点や何人かで調理するには狭いと感じることがデメリットとして挙げられます。
「独立型キッチンの長所、短所」
従来どおり女性の城といった雰囲気になるのが独立型のキッチンです。調理に伴う音や匂いを気にすることなく調理に専念できるのがメリットでしょう。
しかし、目が離せない幼児がいる場合でも子どもを見ながら調理はできませんし、料理の提供や後かたづけにも多少手間がかかります。ダイニングとのスムーズな動線を確保することが重要になります。
次に、リビングと和室の関係です。リビングと和室を続きで設けるか、それぞれ別に設けるかによっても毎日の暮らしは大きく変わってきます。
【和室とリビングを続きで設ける場合】
メリットとしては、必要に応じて続きで広く使えることや普段の生活でも和室をリビング的に使えること、間口が狭く奥行きの長い敷地でもプランを立てやすいといった点が挙げられます。
欠点としては、来客を和室に通したときLDKの音がよく聞こえてしまう点やプラン上廊下が長くなってしまうことがあります。
【それぞれ独立して設ける場合】
長所としては、LDKの音が気にならない点や普段の使用による劣化が少なくなる点。短所としては、使用頻度が少ない部屋になってしまう可能性があることや間口の狭い敷地ではプランが難しい点、来客の人数が多いときでも広く使えない点があります。
都市部など狭小敷地で最近増えている3階建ての場合も、LDKを1階にするか2階にするかの選択があります。
【LDKを1階にする場合】
長所は買い物の持ち運びや来客の出迎えが楽なこと、必要なときだけ上階に上がればよいこと。逆に短所として、広い空間をとりづらい点やお年寄り用の部屋が1階に設けられなくなる可能性があります。
【LDKを2階にする場合】
長所としては、日当たりが確保しやすい点や1階よりも広い空間を確保しやすい点が挙げられます。短所は、何かあればいちいち1階まで下りなければならないなど動線が長くなることです。
以上のようにプランを考える際には、それぞれの長所、短所を具体的なイメージで比較検討しながら自分たちのライフスタイルや家族構成に合ったプランを採用していくことが大切になります。
また、住宅メーカーから上がってきた平面図も、工夫しだいで最適なプランを検討するとても有用なツールになります。
もちろん、間取りなどが書かれた平面図を漠然と眺めていても具体的なイメージはわいてきません。厚紙などを使って図面と同じスケールのソファーやテーブル、椅子、テレビ、ベッドなどの形を作り、平面図上の置きたい部屋に置いてみるとよいでしょう。
その部屋の広さが適正かどうか、また使い勝手はどうなのかといった具体的なレベルでプランが検討できます。
使いやすい間取りかどうかは、実際にその間取りでの生活を想定しながら家族それぞれの一日の行動を平面図にマーカーなどで書き込みます。すると、家族が集中する場所や動きが交錯する場所、あるいは渋滞する場所などがわかり、使いやすい間取りにするための大きなヒントになります。
風通しも、平面図から判断することができます。風を取り入れるため大きな窓を設けたとしても、風が抜けるための窓がなければ思ったほどの効果は上がりません。
風を取り入れる窓の対角線上にあるのが理想ですが、無理な場合はそれに近い場所に小窓を設けることで風の通り道ができます。
一見、無味乾燥な住宅の平面図ですが、理想のプランづくりに向けて大いに活用してほしいものです。

Copyright © 2014 「へやみけ」 All Rights Reserved.