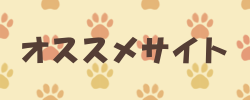平成27年10月最新記事PICKUP!
工場購入・建設に使える事業再構築補助金
"工場購入・建設に使える事業再構築補助金の活用法
【事業再構築補助金の概要や要件】
事業再構築補助金は、コロナ禍における経済活性化を目的として、工場購入・建設を行う事業者に対して支給される補助金の一種です。公募期間や要件は事業再構築補助金のウェブサイトに詳細が掲載されています。申請者は要件を満たしていることを事前に確認し、申請の際に必要な書類を準備することが重要です。
【事業再構築補助金を活用する具体例】
事業再構築補助金を活用する具体例としては、新しい工場の建設や設備の導入などがあります。補助金を活用することで、建設費用の一部を補填し、経営の安定化や事業の拡大を図ることができます。また、補助金の申請方法や条件については、各自治体のホームページや専門サイトで確認することができます。
【まとめ】
工場購入・建設に使える事業再構築補助金は、事業拡大や経営安定化を図るための重要な支援制度です。申請に際しては、公募期間や要件をしっかりと把握し、必要な書類を準備することが大切です。また、具体的な事例を参考にしながら、自社の事業計画に合った補助金の活用方法を模索してみましょう。"
最新コラム!2015年10月
- 平成27年10月1日新着!
- 「独身世帯」
-

- 結婚しない「独身世帯」が増えていることもあげられる。住宅は価格的にも需要でも頭打ちというのは、問違った考えであることがわかる。それも大都市だけの問題ならいざ知らず、全国的に持ち家率が低下しているところを見ると、
- 平成27年10月2日PICKUP
- 不動産業者は法律に縛られて営業をしている
-

- ■悪質な業者かどうかを見分ける 一般に不動産業者と言われるが、これは正式には「宅地建物取引業者」である。 この業者が、家や土地、マンションなどの不動産の売買に際して、法律上、業務としてそれ を行なうことが
- 平成27年10月3日更新
- 免許の表示と宅地建物取引主任の役割
-

- ■必ず宅建主任であることの確認を 不動産の売買では、表面的には、営業マンが大変重要な役目を果たす。これは我々が不動産業者のところに行った時に、まず最初に接触するのが、営業マンだからである。そこで気をつけなけれ
- 平成27年10月4日最新情報
- 都市計画法上のさまざまな制限
-

- ■用途、目的、環境によって種別されている 土地の利用には、さまざまな制限が都市計画法によって定められている。そのために、それぞれの地域や、どんな道路に面しているかによって、建てられる建物の種類や広さ、大きさが
- 平成27年10月5日NEWS
- 用途による制限の内容
-

- 1) 第一種低層住居専用地域 3階までの建物しか建てられないという規制がある。最も条件の厳しい地域で、そのぶん住 環境としては望ましい 2) 第二種低層住居専用地域 小さな生活回りの店にかぎり建設を認め
- 平成27年10月6日新着!
- 建ぺい率と容積率についての決まり
-

- ■敷地に対する建物、延べ床面積の割合 建物を建てる時に非常に重要なのが、「建ぺい率」と「容積率」である。 これは、都市計画区域内で防災や日照のことを考えて建物の規制をするものである。一戸建 てにかぎらず、
- 平成27年10月7日PICKUP
- 道路と袋地に関する規制
-

- ■接道義務に準じているか 建物を建てるには、必ず道路に接していなければならない。このことを「接道義務」といっている。どれだけ接していなければならないかというと2メートルである。昔ながらの町並みや、農道であった
- 平成27年10月8日更新
- 私道として認められる条件
-

- ■私道として認められる条件 住宅は、必ずしも公道に面しているものばかりではない。ミニ開発の住宅などでは、「位置指定道路」というものがあり、その私道に面している。そこで「私道」とはどのようなものであるかを説明し
- 平成27年10月9日最新情報
- 高さによる建物の制限
-

- ■空間や日照を確保するため制限 建築基準法によって建物の高さも制限されている。まず、基本的に第一種・第二種低層住宅専用地域では10mまたは12m、第一種・第二種中高層住宅専用地域、第一種・第二種住居地域 で
- 平成27年10月10日NEWS
- 隣地境界線からの外壁の後退
-

- ■隣家ともめないためにも充分な考慮を この他に重要なのは、東側、西側など、「斜線制限」のないところである。一般的には、都市計画法上で外壁の後退が定められた地域では、隣地境界線から1メートル~1.5メートルの距
- 平成27年10月11日新着!
- 規模、構造、品質
-

- 建物は、規模、構造、品質など千差万別で建物価格そのものの総合的なデータは、ありません。それに代わるものとし て、建築費に関するデータがあります。それは、「標準建築費指数」と「全国木造建築費指数」の資料です。ま
- 平成27年10月12日PICKUP
- 土地の価格データ
-

- 土地の価格データは、評価額をもとにして成り立っています。その点が卸売物価指数や消費者物価指数などの一般の物価の場合と異なっています。この点を簡単にコメントします。公示価格、都道府県調査の基準地価格、市街地価格指
- 平成27年10月13日更新
- 軟弱地盤
-

- 軟弱地盤の上に建つ家は、地震の際に家が傾いたり陥没してしまう危険性があるので事前の対策が必要です。地盤の弱い家に建つ家は、大地震の際に家が傾いたり陥没してしまう危険性があります。こういった土地は「軟弱地盤」と呼
- 平成27年10月14日最新情報
- 「絶対大丈夫」な対策はない
-

- 軟弱地盤に家を建てるというのは、砂の固まりの上に家を建てているような感じです。そのようなところに家を建てているのですから、当然のように地震に対しても揺れやすくなります。その対策として「支持地盤」という、軟弱地盤
- 平成27年10月15日NEWS
- 「デザインに凝った家」は、何かと問題あり
-

- 揺れに強い家を作るには、きちんとした構造計算がなされる必要があります。構造計算とは、建物を設計する際に、地震などに対する安全性を計算することです。阪神・淡路大震災の際にも、きちんと構造計算している建物は、倒壊せ
- 平成27年10月16日新着!
- 建物の安全を確保
-

- ●安全を守るために必要なこと 建物の安全を確保するうえで、建築基準法は最低限のルールを定めています。つまり、建築基準法を満たすのは当然として考え、建物の安全は構造計算の安全性レベルをいかに引き上げるか、にかか
- 平成27年10月17日PICKUP
- 揺れに弱い建物の特徴
-

- 阪神・淡路大震災の資料を見ると、木造、鉄筋、鉄骨といった工法を問わず、古い建物の倒壊する割合が高いことがわかっています。特に昭和56年(1981年)以前に建てられた建物の倒壊比率は高いことが指摘されています。戦
- 平成27年10月18日更新
- 「昭和56年がボーダーライン」の理由
-

- なぜ「昭和56年」がボーダーラインになるのでしょうか。同年に建築基準法施行令が大改正され、耐震設計基準が大幅に改正されたという背景があります。これは、昭和53年(1978年)に起きた宮城県沖地震の被害を教訓に行
- 平成27年10月19日最新情報
- 地盤の上に家を建てるのが基本
-

- 揺れない家を作る上では、しっかりした地盤の上に家を建てるのが基本です。しかし、現実には、「軟弱地盤」のように、不安定な土地に家が建てられるケースがあります。そのような注意すべき土地のひとつに、盛土などによる造成
- 平成27年10月20日NEWS
- 業者の仕事しだいで安全が左右される
-

- ●業者の仕事しだいで安全が左右される しっかりとした施工が大切なのは、木造住宅に限らず、どの工法で家を建てる場合でも同じです。たとえば、基礎のコンクリートは施工のよしあしに大きく左右されます。特に建築業者が忙
- 平成27年10月21日新着!
- 不動産贈与と現金贈与はどちらが有利か
-

- 贈与税を計算する際の土地や建物の価額は,通常の売買価額ではなく,相続税評価額で行われます。一般的に,相続税評価額は時価相場の8割程度といわれておりますので,相続税評価額で2,000万円の居住用不動産を贈与すると
- 平成27年10月22日PICKUP
- 持分贈与はどうすれば有利か
-

- たとえば,建物の評価額1,000万円,敷地の評価額5,000万円の居住用不動産を所有している夫が,贈与税が課税されない範囲で妻にその居住用不動産を贈与しようという場合には,居住用不動産の一部を贈与するということ
- 平成27年10月23日更新
- 店舗兼住宅でも特例が受けられます
-

- 自分の住まいが店舗兼住宅のような場合には,配偶者贈与の特例が受けられるのかどうかという疑問が生じます。たとえば,店舗部分と居住用部分の面積がともに2分の1ずつである店舗兼住宅(敷地を含む。以下同じ)で,相続税評
- 平成27年10月24日最新情報
- 所得税の計算の仕方
-

- アパートや駐車場を賃貸している場合には,家賃収入や地代収入が生じますが,その収入金額(総収入金額)が,その収入を得るためにかかった費用の金額(必要経費)を超えるとき,つまり利益(所得)が生じたときは,その利益は
- 平成27年10月25日NEWS
- 経費にできるもの01
-

- (1)租 税 公 課 固定資産税や都市計画税,事業税など,貸付けに供している土地や建物について支払う税金は必要経費となります。 (2)損害保険料 火災保険料など,貸付けに供している建物等に掛けている損害保
- 平成27年10月26日新着!
- 経費にできるもの02
-

- 減価償却費 土地などは,古くなったからといって値うちがなくなったなどということはありませんがそれにひきかえ,建物などは,建ててから20年もたてば,ペンキがはげたりあちらこちらが傷んだりしてきて,新築の時よりも
- 平成27年10月27日PICKUP
- 経費にできるもの03
-

- 借入金の利息 アパートやマンション等の賃貸用の資産を取得する際に借入れをしている場合には,その借入金の利息については必要経費となります。ただし,実際に賃貸するまでの期間は建物の取得価額に算入されますので注意し
- 平成27年10月28日更新
- 青色申告は10万円得(青色申告控除)
-

- 所得税の申告書を青色申告書で提出している場合には,青色申告控除として不動産所得の金額から10万円を控除することができます(ただし,不動産所得の金額が10万円未満の場合には,その金額までとなります)。この青色申告
- 平成27年10月29日最新情報
- 建物の付随費用は(減価償却資産の取得価額に含まれるものはどんなものか)
-

- 建物等は,その取得価額を減価償却の方法によって費用化していきますにのように減価償却により費用化していく資産を減価償却資産といいます)。このため,減価償却を行うには,まずその計算の基となる取得価額を決めなければな
- 平成27年10月30日NEWS
- 建物の付随費用は(減価償却資産の取得価額に含まれるものはどんなものか)02
-

- 旧建物の取り壊し費用等 アパート等を建てるために土地を買おうとする場合に,その土地が何も建っていない更地であるとは限りません。目当ては土地でも,その上に前の持主の建物が建っているため,土地だけでなく建物ごと買
- 平成27年10月31日新着!
- 建物の貸付が事業的規模であるかどうかの判定
-

- アパート等の賃貸が事業的規模で行われているかどうか,つまり,事業といえるほど大きな規模で行われているかどうかによって,取り扱いが違ってくることがあります。その事業的規模であるかどうかは,家賃収入の状況や,そのア