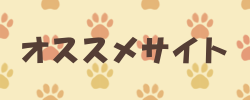父親の空間をつくる
2018年3月5日「月曜日」更新の日記
-

- 父と子の間に対話がないのは、父親が家にいる時間が少ないことも大きな要因だ。
現在の多の父親は、「定時制市民」といわれるくらい家にいない。
どうして家にいないのか。
遠距離通勤がひとつの原因であることは明らかだ。
大都市などではそれが最大の原因といってよいかもしれない。
家を買えば遠くへ行かざるをえない。
そのローンを返すために残業を続けるということもあろう。
ここにも現在の住宅事情が忍びこんで家庭の団らんを奪っている。
そのほかに私は、最近の家には書斎がないことも作用しているのではないかと考えている。
会社から帰っても家の中でゆっくりすることができないと思い、あるいはラッシュアワーを避けて、新宿や梅田でつい1杯やってから帰るというサラリーマンも多いのではないか。
近頃のビジネス社会は驚くべき速さで変化している。
やれ情報革命だ流通革命だOA機器の導入だというふうに。
父親はその変化に対応するために勉強しなければならない。
しかし家には書斎がない。
父親専用の机すらないというのが多くの家庭の現状だろう。
これでは社会の変化についていけない。
書斎がなければ、父親のための書斎コーナーだけでも確保する必要があると思う。
そうすればちょっとした仕事は家でやれる。
勉強もできる。
父親もすこしは早く帰る気持にもなろう。
また、居間が小さいことも親子の対話をさまたげている。
小さな居間の中では、だれかがテレビをつけるとその場の全員がテレビを見ざるをえなくなってしまう。
母親が「テレビばっかり見ていないで勉強しなさい」と、子どもを個室に迫いやってしまう。
ますます対話はできなくなる。
私はイギリスに留学中、下宿生活をしていた。
その家は公務員の家庭だったが、居間は30畳ぐらいはあった。
大きな部屋だから、家族全員が集まってきてもそれぞれに別々のことができる。
気にもならない。
そして必要があれいつでも声をかけて話し合うことができる。
その家の主は研究者であるにもかかわらず書斎をもっていなかった。
彼はいつも居間の片隅の大きな机で書きものや読書をしていたが、その合問に家族と話もしていた。
これが居間のひとつのあり方だろうと思う。
居間はまず広くなくてはいけない。
最低20畳は必要だろう。
子ども部屋は小さくてもよい。
居間が広ければ子どもはそこで勉強する。
対話もできる。
だれかがテレビを見ても、邪魔にならない。
どうしても1人になりたければ、個室へ引っこめばよい。
居間は、日照・通風などを考慮してできるだけ快適にしなければならない。
居間の快適さが、家族団らんの条件のひとつでもある。

Copyright © 2014 「へやみけ」 All Rights Reserved.